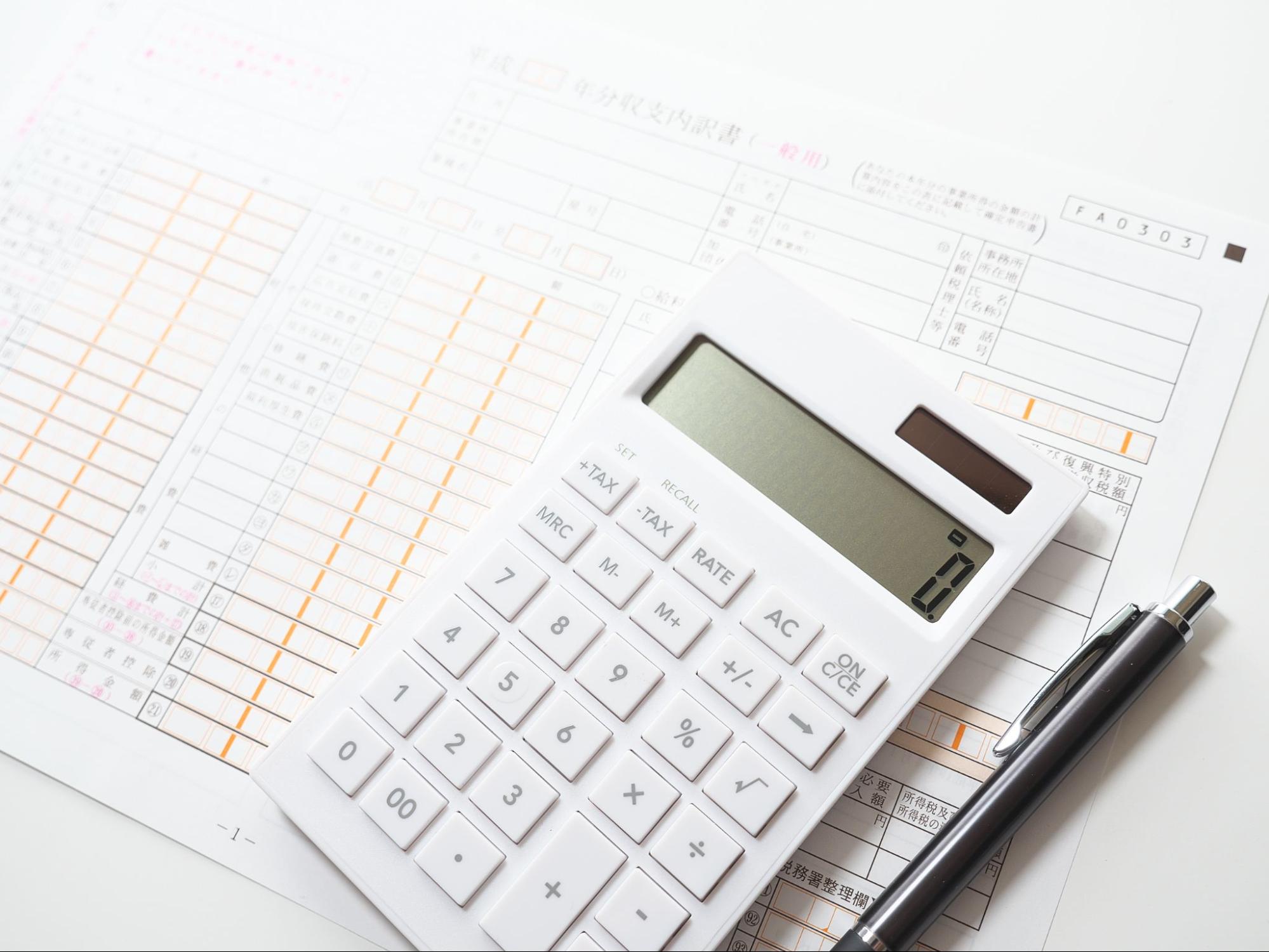
歯列矯正は、歯並びや不正咬合を改善するために行われますが、費用が高額になることから経済的負担を感じ、医療費控除の利用を検討する方も少なくありません。
しかし、実際に矯正歯科での治療が医療費控除の対象になるのかわからず、治療に踏み切れない方もいます。
この記事では、歯列矯正が医療費控除の対象になるのか、その条件や申請手続きの流れなどを紹介します。
歯列矯正を受ける前に医療費控除について知りたい方、すでに支払った費用の控除を検討している方は、ぜひご覧ください。
医療費控除とは
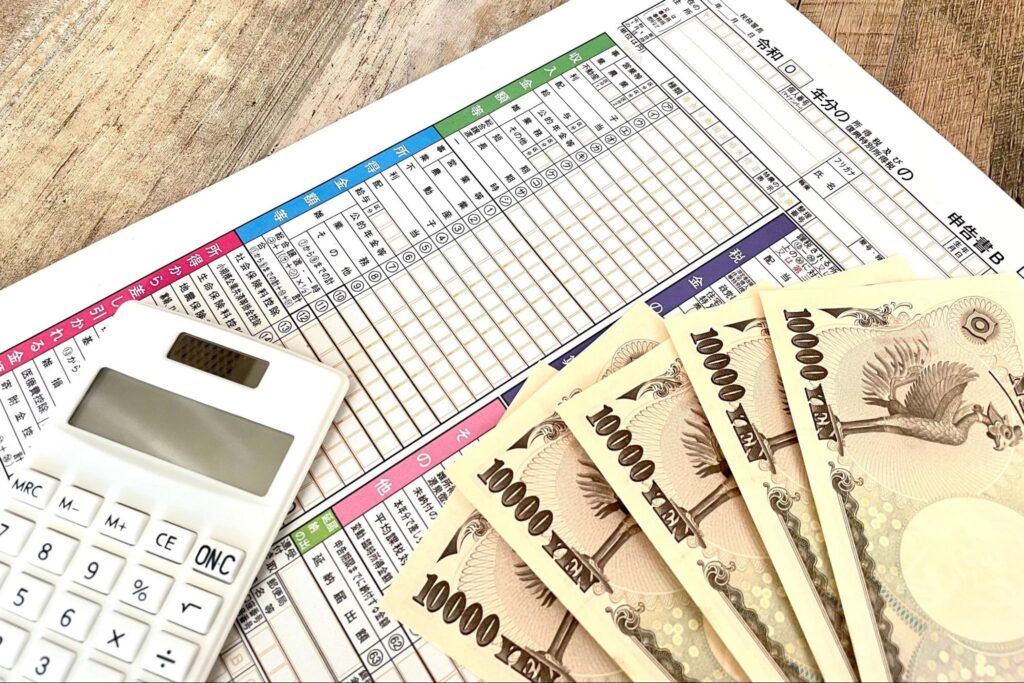
医療費控除は、確定申告によって税金の負担を軽減できる制度ですが、どのようなものなのかわからない方もいます。
まずは、医療費控除の概要や対象について紹介します。
医療費控除の概要
医療費控除とは、1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
本人だけではなく、生計を共にする配偶者や親族も合算対象です。
申請には領収書やレシートが必要となるため、支払った医療費分を大切に取っておく必要があります。
医療費控除の対象となるもの
医療費控除は、以下のような費用が対象となります。
- 通院費
- 入院費
- 医薬品費
- 医療器具費 など
通院費や入院費なども対象となる一方で、自家用車のガソリン代や審美目的で行う治療などは対象外です。
詳しくは、国税庁のホームページを確認しましょう。
控除対象になる金額の計算方法
控除対象になる金額は、以下のように計算します。
| (支払医療費合計-保険金などで補填された額)-10万円(または所得金額×5%のうち少ない方) |
支払った医療費の合計から、保険金等で補填される金額をマイナスする必要があるため注意してください。
また、医療費控除の最高額は200万円です。
矯正歯科の医療費控除について
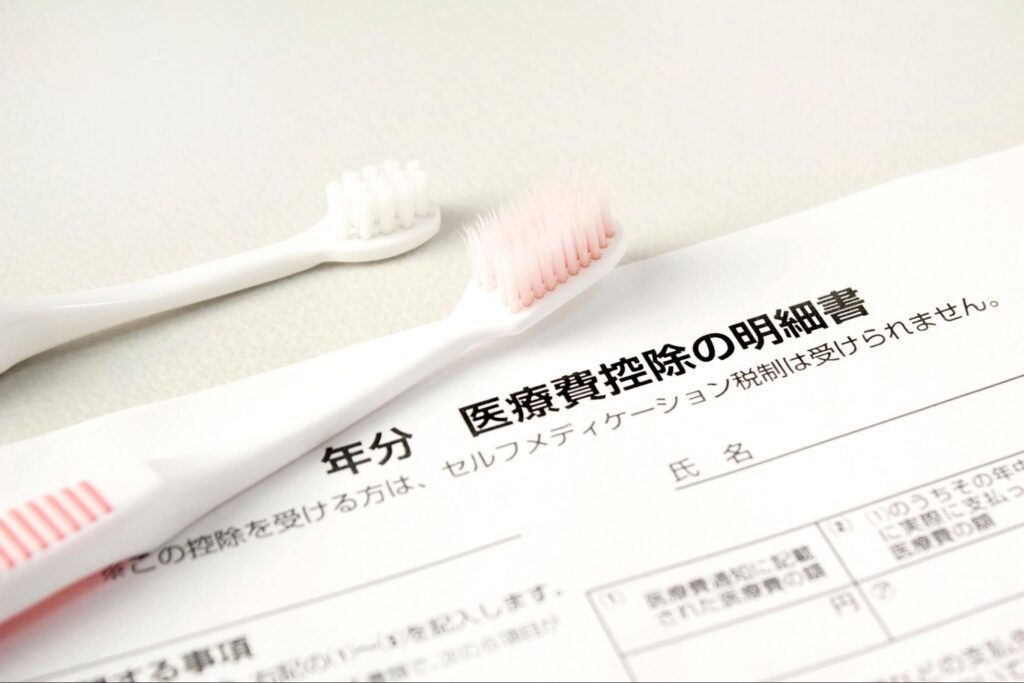
医療費控除は、高額な医療費を支払った際に有効な制度ですが、矯正歯科での治療は対象になるケースとならないケースがあります。
ここからは、矯正歯科の医療費控除について紹介します。
子どもの歯列矯正
成長期の開咬や反対咬合などの不正咬合は、顎の発育を阻害する恐れがあります。
結果的に、将来の咀嚼や発音、顎骨の正常な発育に影響を及ぼすと判断される場合、子供の歯列矯正は医師の判断に基づいた医療目的と認められます。
医療目的の歯列矯正であれば控除の対象となり、一般的に多くのケースが対象です。
大人の歯列矯正
大人の歯列矯正で医療費控除となるのは以下のケースです。
- 咀嚼機能障害
- 発音障害
- 顎関節症
- 虫歯や歯周病のリスク軽減
これらの機能改善を目的とした「治療目的」で歯列矯正を行うと医師が判断した場合、医療費控除の対象となります。
しかし、審美目的(見た目の向上)としての治療は対象外で、医師の診断による明確な目的の提示が必要です。
(参考:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」)
治療目的であることが条件
医療費控除の対象となるには、「治療目的であること」が大前提であるため、歯科医師による診断が重要です。
また、審美目的と機能回復が重なっているケースでも、治療目的と判断されれば対象となる可能性があります。
まずは矯正歯科で診断を受ける必要があるため、医療費控除を利用して歯列矯正を検討したい方は、矯正歯科を受診してカウンセリングを受けてみてください。
医師の診断書や証明書は基本的に不要
医療費控除に医師の診断書や証明書は原則不要です。
しかし、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、医師に「治療目的である」ことを記載しておいてもらうとよいでしょう。
医療費控除を利用して歯列矯正を検討している方は、治療開始前に歯科医師に相談することをおすすめします。
診断書ではなく領収書への記載でも問題ありませんが、後から税務署に診断書の提出を求められる場合もあります。
後から診断書の提出を求められるケースは、以下のような場合です。
- 税務署からの照会の連絡
- 審美目的か治療目的か判断が難しい
- 明細書の記載内容に不自然な点がある
このような場合に、診断書を後から取得することも一般的には可能です。ただし、別途診断書発行のための手数料がかかる場合があるため注意が必要です。
通院記録やカルテなど、歯科医院に残っている資料で対応できる場合もありますが、税務署に早めに判断してほしいなどの希望がある場合は、診断書があると安心です。
実際の医療費控除申請の流れ
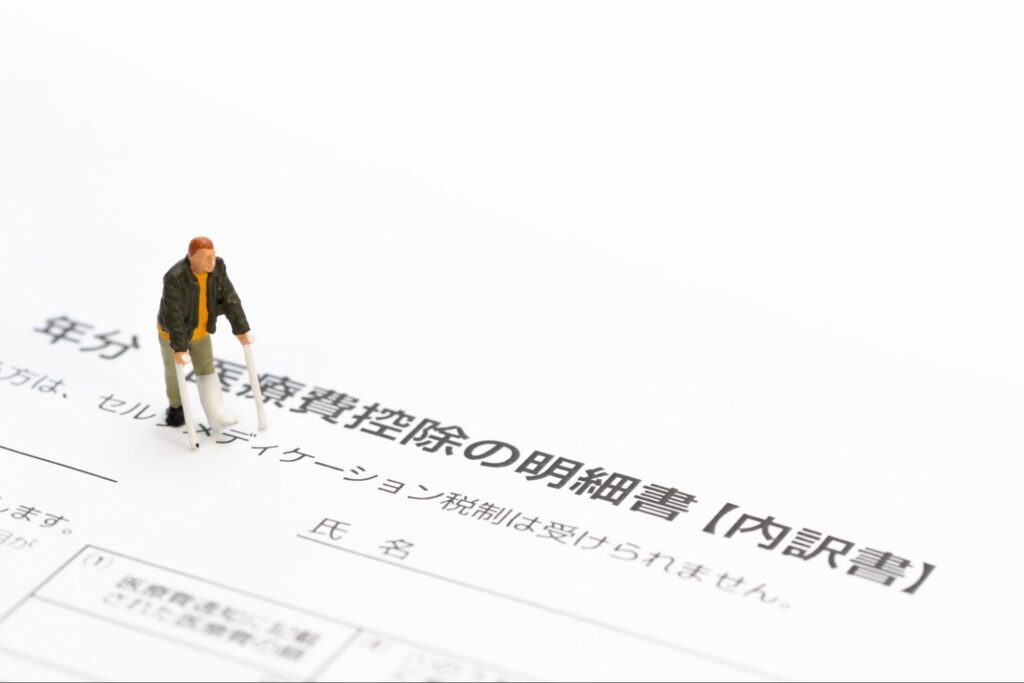
ここからは、実際に医療費控除を利用する際の申請の流れを紹介します。
必要な書類
実際の医療費控除は、確定申告によって行います。確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書(A様式/B様式)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 医療費控除の明細書(国税庁フォーム使用可)
- 治療の領収書・薬局の領収書
- 通院交通費記録
- デンタルローン契約書・支払明細(必要な場合)
- 還付金受取口座情報・本人確認書類
領収書は、申告の際に提出する必要はありませんが、5年間は保存する義務があるため注意が必要です。
確定申告書の記入方法
医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に転記します。
明細書には、家族全員分の医療費を書き込み、合計額を算出してください。
申告する際は、税務署へ確定申告書を持参や郵送もできますが、e-Taxによる申請は自宅で完結できるため便利です。
e-Taxを使ったオンライン申請の手順
e-Taxによるオンライン申請は、以下の手順で行います。
- 国税庁のe-Taxサイトにアクセス
- マイナンバーカードで認証を行う
- 医療費控除の明細書をアップロード
- 申告データの入力
- 電子署名付与
- 還付金口座の登録
- 申告データ送信
提出が完了したら、還付金が約2カ月以内に指定口座に振り込まれます。振り込まれる時期は個人差があるため、メールやマイページなどを確認しましょう。
医療費控除のシミュレーション

例えば、年収が500万円の方が年間30万円の医療費を支払った場合、以下のように自己負担額の医療費控除額を計算できます。
| 30万円-10万円(※所得が200万円超のため)=控除対象額20万円 |
この金額をもとに所得税、住民税が還付される仕組みです。
実際の還付額は、個人の所得や税率によって異なりますが、例えば所得税20%、住民税10%の場合は6万円程度の還付が期待できることになります。
また、所得構成によって金額は異なると覚えておきましょう。例えば、そもそも所得が少ない方の場合は、控除しても還付される税金があまりないということもあります。
矯正歯科で医療費控除を受ける際の注意点

矯正歯科で医療費控除を受ける場合、治療目的であること以外にもいくつか注意すべき点があります。
ここからは、矯正歯科で医療費控除を受ける際の注意点を紹介します。
通院費(交通費)も対象になる
医療費控除の対象となる通院に関しては、通院費も控除対象になります。
ただし、公共交通機関を利用する必要があり、自家用車のガソリン代や駐車場代は含まれません。
やむを得ない事情があって自家用車で通院する場合は、税務署との個別対応になるため問い合わせてみましょう。
デンタルローンやクレジットカード払いの場合
デンタルローンやクレジットカード払いの分ももちろん申請できますが、金利や手数料は対象外となるため注意が必要です。
対象となる治療費のみが申請できるため、しっかりと計算して控除される額を算出する必要があります。
複数年にわたる治療費の場合
複数年にわたって支払いがある場合は、支払った年ごとに別々に申請が必要です。
治療開始年に一括で支払った際はその年に申請すればよいですが、支払いが年をまたいでいる場合はいつどの程度支払ったかを明確に記録しておきましょう。
申請し忘れた場合
医療費控除は、申請し忘れても過去5年以内であれば「更正の請求」によって申告が可能です。
ただし、領収書が必要となる点は注意が必要です。
医療費控除の対象になる他の歯科治療

歯科医院では、歯列矯正以外にもいくつかの治療が医療費控除の対象となることがあります。
ここからは、医療費控除の対象になる可能性がある治療を紹介します。
インプラント治療
インプラント治療は、失った歯の機能を補うために顎の骨に人工歯根(インプラント)を埋め込む外科的処置です。
自由診療となるため高額なケースが少なくありません。
1本あたりの費用は30~50万円程度かかることもあります。
インプラント治療が、咀嚼機能の回復を目的としている場合、医療費控除の対象になります。
具体的な例としては、入れ歯が合わないことが原因で生活に支障が出ていて、インプラントを選択するなどです。
ただし、見た目向上のため、単純に金属を使用したくないなどの理由では、対象外となるケースもあります。
医師とのカウンセリングで治療目的を明確にし、診断書や領収書に記載してもらうとよいでしょう。
親知らずの抜歯
親知らずは、正常に生えてこないことが多く、炎症や痛み、歯並びの悪化の原因となるため抜歯が必要と判断されるケースが少なくありません。
そのため、一般的には医療費控除の対象です。
具体的には、横向きに生えている、炎症があり化膿している、歯列矯正の準備などが当てはまります。
一方で、審美目的や患者さんの希望などで抜歯が行われた場合、控除の対象外となることもあります。
入れ歯の作製
入れ歯は、歯を失った際に保険適用でできる治療として選択されます。
咀嚼機能や会話能力の補助を目的とする場合が多く、治療目的とみなされ控除の対象になることが一般的です。
そのため、初めて入れ歯を作製する場合だけではなく、調整や修理、再作製なども控除対象になるケースが多いです。
ただし、セラミックやチタンなどの高級素材や特殊なデザインなど、保険適用外の治療は審美目的とみなされるケースがあります。
医療費控除が利用できないケースと対策
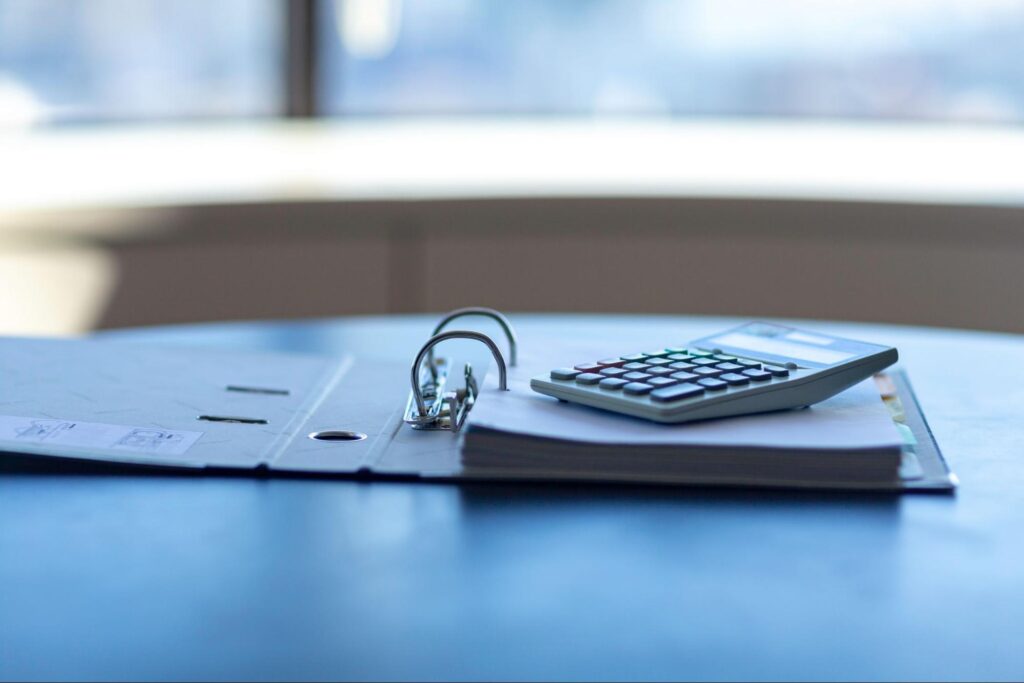
最後に、医療費控除が使用できない具体的なケースと対策を紹介します。
対象外となるケース
審美目的である以下の治療は医療費控除の対象外です。
- ホワイトニング
- ラミネートべニア
- 審美矯正(機能に問題がない場合)
- セラミッククランへの変更(見た目重視)
患者さん本人が希望した任意治療は、医療費控除の適用外です。
また、繰り返しになりますが、自家用車のガソリン代や駐車料金も原則控除されない点には注意が必要です。
例外として、公共交通機関がない地域や緊急時、子どもや高齢者の付き添いなどは個別対応が可能なケースもあります。
控除対象にならなかったときの相談窓口
税務署で否認されてしまった場合や、どの費用が対象かわからないなどトラブルが生じた際は、以下の窓口に相談しましょう。
- 税務署
- 税理士
- ファイナンシャルプランナー(FP)
お住まいの地域の税務署では、医療費控除の相談窓口が設置されています。2月中旬~3月中旬に行われる確定申告の時期は、特設窓口や電話窓口が開設されることもあります。
提出書類の確認やどこまでが対象になるかなど、不明点は早めに税務署に相談しておくと安心です。
また、税理士やファイナンシャルプランナーにも相談可能です。
年間医療費の計算が複雑な方や、家族で複数の医療費がある方、デンタルローンがあって今年度分の計算がわからない方などは、相談してみましょう。
初回相談無料サービスやオンライン相談に対応しているところも多いため、活用することをおすすめします。
まとめ
矯正歯科での治療は、審美目的ではなく治療目的の歯列矯正であれば、医療費控除の対象になります。
子どもの歯列矯正は対象となることが一般的ですが、大人の場合はカウンセリングで歯科医師としっかり相談する必要があります。
また、歯列矯正以外にも歯科医院での治療で医療費控除の対象となるものがあるため、治療目的で行った処置があれば領収書を保管しておきましょう。
お花茶屋ハル歯科・矯正歯科では、適切な診断によって治療を提案させていただきます。
医療費控除に関するご相談にも対応するため、まずはお気軽にご来院ください。
