
「虫歯にはなっていないのに奥歯が痛い」
「夜になると奥歯が痛むが、原因がわからない…」
など、奥歯の痛みに悩んでいる方は少なくありません。
奥歯が痛む代表的な原因としては「虫歯」がありますが、それ以外にも原因が存在します。
この記事では、虫歯以外で奥歯が痛む理由を「歯原性歯痛(歯や歯茎)」「非歯原性歯痛(歯以外)」に分けて詳しく解説します。
夜に痛みが強くなるメカニズムや、歯科医院を受診するまでに痛みを和らげる応急処置方法も解説しますので、つらい痛みに悩まされている方はぜひ記事をチェックしてみてください。
虫歯じゃないのに奥歯が痛むことはある?

奥歯の痛みの原因の多くは虫歯ですが、それ以外にも痛みを感じるケースは数多く存在します。
ここでは、奥歯に感じる痛みについて解説します。
歯原性歯痛と非歯原性歯痛
奥歯に生じる痛みの原因は、大きく「歯原性歯痛」と「非歯原性歯痛」の2つに分けられます。
- 歯原性歯痛(歯や歯茎の問題)
- 非歯原性歯痛(歯以外の問題。筋肉や神経、ストレスなど)
歯原性歯痛とは、歯や歯茎に由来する痛みのことです。虫歯以外では、知覚過敏、親知らず、歯周病、歯髄炎などが該当します。
一方、非歯原性歯痛は、歯や歯茎に問題ないのに起こる歯痛のことです。筋肉の緊張、神経の異常、ストレス、病気などが関係しており、原因不明のケースもあります。
不要な治療・抜歯をされてしまうケースもある
患者さんがあまりに痛みを訴えるため、抜髄(歯の神経を抜くこと)や抜歯などが行われるケースがあります。
しかし、「非歯原性歯痛」による痛みであった場合、歯や歯茎の治療をしても痛みはよくなりません。
歯を削る、神経を抜く、抜歯といった治療は、一度行えばもとに戻すことはできないため、詳しい検査で痛みの原因をしっかり見極めたうえで、必要な治療を行うことが大切です。
【歯や歯茎の問題】虫歯じゃないのに奥歯が痛む原因と対処法
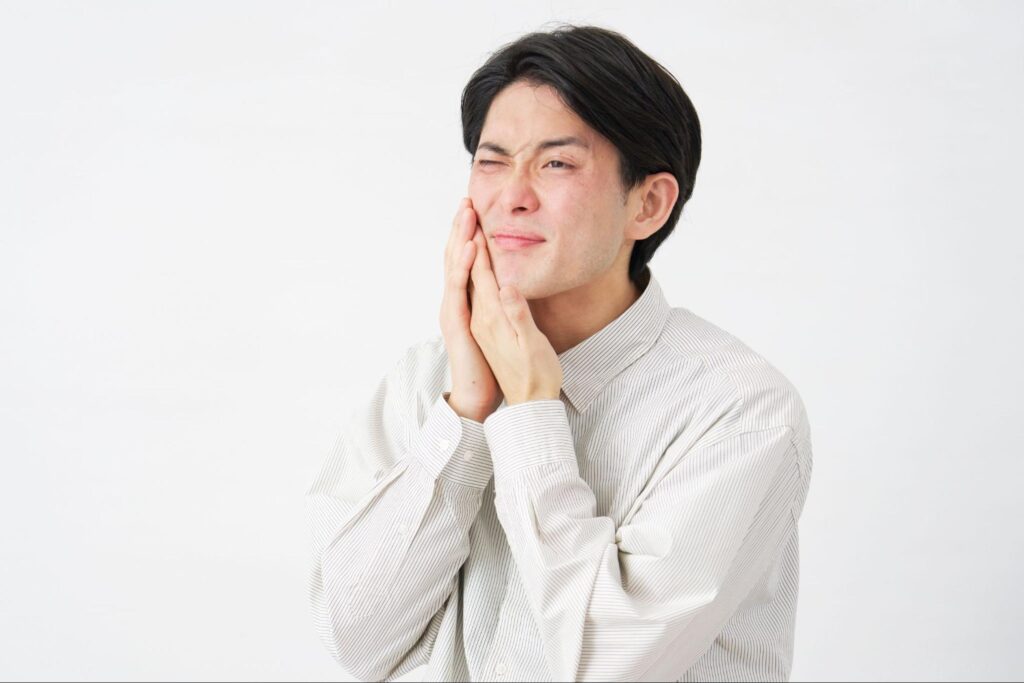
虫歯以外でも、歯や歯茎の問題によって奥歯に痛みが生じることがあります。考えられる原因は、以下の通りです。
- 知覚過敏
- 親知らずによる痛み(智歯周囲炎)
- 歯周病の進行
- 歯髄炎や根尖性歯周炎
- 噛み合わせに問題がある
- 歯根膜炎(歯ぎしり・食いしばり、外傷)
- 歯根破折
- 治療で神経が傷ついている(外傷性神経障害性疼痛)
それぞれ詳しく解説します。
知覚過敏
虫歯がないのに冷たい飲み物や歯磨きで歯が「しみる」ように痛む場合は、知覚過敏(象牙質知覚過敏症)かもしれません。
歯の表面のエナメル質がすり減ったり、歯茎が下がって象牙質が露出したりすると、神経が刺激に敏感になり痛みを感じやすくなります。
知覚過敏は虫歯や歯周病、過度なブラッシング、歯ぎしりや食いしばり、酸蝕歯(酸で歯の表面のエナメル質が酸が溶けてしまった歯)などが原因です。
- 歯科医院で知覚過敏の薬の塗布・コーティング
- 虫歯や歯周病など原因の治療
- ナイトガード(マウスピース)
- ブラッシング方法の見直し
- 知覚過敏用の歯磨き粉を使ったセルフケア
知覚過敏用の歯磨き粉を使ったり、ブラッシング方法の見直しなどで予防・対策ができるためぜひ実践してみましょう。
親知らずによる痛み(智歯周囲炎)
親知らずが横向きや斜めになって生えてくると、歯茎や隣の歯が圧迫されて痛むことがあります。
また、正しく生えてこない親知らずは周囲に汚れがたまりやすくなり、周囲の組織に炎症を引き起こすことがあります。
これを智歯周囲炎といい、歯茎の腫れや膿といった症状が起こるほか、悪化すると口が開きづらくなったり、周囲からもはっきりわかるほど顔が腫れることもあり、注意が必要です。
- 歯茎の洗浄
- 抗生物質の服用や点滴
- 親知らずの抜歯
親知らずによる痛みや智歯周囲炎は、上記のような方法で治療します。
重症化し頬部蜂窩織炎(きょうぶほうかしきえん)となると入院治療が必要となるケースもあるため、悪化する前に対処することが重要です。
歯周病の進行
歯周病が進行すると、歯の周囲にある組織が炎症を起こし、噛んだときに痛みを感じることがあります。
歯茎の腫れ、出血、歯が浮くような感覚があれば、歯周病かもしれません。
- 口腔ケアの徹底(ブラッシング指導)
- 歯垢や歯石の除去(スケーリング、ルートプレーニング)
- 歯周外科治療(フラップ手術)
- 抗生物質の服用
歯周病の予防と改善には、正しい歯磨きと定期的な歯科検診が欠かせません。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスも活用し、歯と歯茎の境目のプラークを丁寧に除去しましょう。
歯周病は放置すれば歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、歯が抜け落ちてしまうため、悪化する前に対処することが重要です。
歯髄炎や根尖性歯周炎
歯の神経が炎症を起こす歯髄炎や、歯の根の先に膿がたまる根尖性歯周炎も奥歯の痛みの原因です。
虫歯や歯周病、歯ぎしりや食いしばり、外傷などが原因で引き起こされ、ズキズキと強い痛みを感じることもあります。
- 根管治療
- 抗生物質の服用
- 抜歯
抗生物質の服用や根管治療によって治療しますが、歯の保存が難しく抜歯が必要となるケースもあります。
大切な歯を失わないためにも、早めの治療が重要です。
噛み合わせに問題がある
上下の歯の噛み合わせにズレがあると、一部の歯に過度な力がかかり、歯根膜炎を発症して痛みが起こることがあります。
歯根膜炎とは、歯の根と骨の間にあるクッションのような組織「歯根膜」に起こる炎症のことです。
刺激されなければ症状は治まっていきますが、噛み合わせに問題がある場合は慢性的に負担がかかり続けるため、悪化して神経を失ったり、抜歯が必要になったりする可能性があります。
- 噛み合わせの調整(歯を少し削る)
- ナイトガード(マウスピース)
- 矯正治療
「歯並びはきれいに見えるものの、実は噛み合わせが良くない」というケースもあるため、一度しっかり歯科医院で確かめてもらい、適切な方法で治療することが大切です。
歯ぎしり・食いしばり、外傷
歯ぎしり・食いしばりや外傷も、歯根膜炎による痛みを引き起こす原因です。主に以下のような方法で治療します。
- ナイトガード(マウスピース)
- 咬筋ボトックス注射
- ストレス管理
- 生活習慣の改善
- 薬の服用や歯の固定(外傷の場合)
歯ぎしり・食いしばりは無意識で行っており、本人が気づけないことも多いため、歯科医院でチェックしてもらうといいでしょう。
外傷の場合、早期の適切な処置が重要となるため、できる限り早く歯科医院を受診することが大切です。
歯根破折
特に過去に治療を受けた歯や神経を取った歯は弱くなるため、気付かないうちに割れてしまうことがあります。
歯ぎしりや食いしばり、強い衝撃などでも歯根破折(歯が割れること)が起こることがあります。
最初は軽い違和感のみで気付かないこともありますが、徐々に痛みが強くなり、噛むと痛い、歯茎の腫れや膿といった症状が見られるようになります。
- 歯根破折接着修復法
- 抜歯
歯根破折は上記のような方法で治療しますが、見た目では分かりづらく、X線やCTなどによる精密な検査が必要です。
程度によっては抜歯が必要になることもあり、予防が大切です。
治療で神経が傷ついている(外傷性神経障害性疼痛)
歯科治療後、通常は一定期間経過すれば痛みは治まっていきます。
しかし、抜歯やインプラント治療などの手術時に歯や顎の神経が傷ついてしまうと、歯は歯茎を少し触っただけでも痛みが起こることがあり、これを外傷性神経障害性疼痛といいます。
このようなケースでは疼痛治療剤(プレガバリン)や一部の抗うつ薬が治療に用いられます。
(参照:一般社団法人 日本口腔顔面痛学会「“原因不明の歯痛”の原因(非歯原性歯痛)」)
【歯以外の問題】虫歯じゃないのに奥歯が痛む原因と対処法

奥歯の痛みの原因が、歯以外にある場合もあり、これらは「非歯原性歯痛」と呼ばれます。
- 筋肉の疲労
- ストレス
- 気圧(気圧性歯痛)
- 病気の影響
上記の代表的な非歯原性歯痛について、それぞれ詳しく解説します。
筋肉の疲労
歯ではなく、顎や顔周辺の咀嚼筋(咬筋や側頭筋など)の疲労が原因で、歯痛が生じるケースもあります。
筋肉が原因の歯痛を「筋・筋膜性歯痛」といい、筋肉の疲労によって生じる「トリガーポイント(TP)」と呼ばれるしこりを押すと痛みを感じることが特徴です。
鈍く痛むケースが多く、痛みが長く続く人もいれば、痛みが出たりなくなったりする人もいます。
- 筋肉のストレッチやマッサージ
- 消炎鎮痛剤の服用
- マウスピースの使用
- 安静(硬い食べ物やガムを控える)
- 歯列接触癖(TCH)の改善
歯や歯茎に問題がない場合は、口の中以外にも原因がある可能性があるため、かかりつけ医に相談してみることも大切です。
ストレス
強いストレスや不安など精神的な要因により、自律神経のバランスが崩れたり、痛覚が過敏になったりして、歯に異常がないにもかかわらず痛みを感じることがあります。
これを「痛覚変調性疼痛(心因性疼痛)」といいます。
痛覚変調性疼痛の場合、激しい痛みが起こることはまれで、慢性的な痛みが長く続くことが特徴です。歯痛の他、不眠や食欲不振、うつ状態、感覚・味覚異常といった症状が見られることもあります。
ストレスや不安が影響している場合、歯科医院と心療内科が連携して治療を行うこともあります。
ストレスは無意識の歯ぎしり・食いしばりにもつながるため、普段から定期的にストレス解消することが大切です。
気圧(気圧性歯痛・航空性歯痛)
飛行機に乗ったときや標高の高い山に登ったとき、台風などで低気圧が起こったときに痛む場合は、気圧性歯痛の可能性が考えられるでしょう。
歯の中には「歯髄腔」と呼ばれる神経が入るための空間があります。
低気圧でその気圧が変化すると、歯髄腔の気圧も変動し、圧力がかかって歯に痛みが起こることがあります。
ただし、気圧変化による歯痛は、誰にでも起こるわけではありません。虫歯や根尖性歯周炎、治療中の歯がある場合に生じることが多く、予防や治療が可能です。
病気の影響
この他、以下のような病気が原因となって歯に痛みが生じることもあります。
- 神経痛(三叉神経痛、舌咽神経痛)
- 頭痛(群発頭痛、片頭痛)
- 上顎洞疾患(上顎洞炎、術後性上顎嚢胞)
- 帯状疱疹(帯状疱疹性歯痛)
- 心臓疾患(狭心症、心筋梗塞)
- 精神疾患(うつ病、統合失調症)
- その他の病気・薬の副作用の影響
歯の痛みが、狭心症や心筋梗塞による放散痛(関連痛)の場合もまれにあるといわれています。
普段から歯科医院で定期的にメンテナンスを受けることで、大きな病気の早期発見につながるケースもあります。
お口だけでなく全身の健康のためにも、ぜひ歯科医院での定期検診を受けてみてください。
原因不明の痛み(特発性歯痛)
歯や歯茎に原因がなく、さらに非歯原性歯痛のどの分類にも当てはまらない原因不明の歯痛の場合、特発性歯痛と呼ばれます。
はっきりとはわかっていないものの神経ネットワークの異常が原因と考えられており、1:9で女性に多いとされる病気です。
他の科とも連携しつつ、抗うつ薬を使った薬物療法や認知行動療法などによって治療します。
(参照:一般社団法人 日本口腔顔面痛学会「“原因不明の歯痛”の原因(非歯原性歯痛)」)
なぜ?夜に痛みが強くなる原因

夜間に奥歯の痛みが増す理由はいくつかあります。
- 横になることで血液が頭部に集まり、血管が膨張して神経が圧迫される
- 副交感神経が優位になることで血管の拡張が促進され、痛みを感じやすくなる
- 入浴によって血行が促進され、副交感神経の働きが促される
- 無意識の歯ぎしりや食いしばりで寝ている間に負担がかかる
上記のような原因が影響し合うことで、夜は歯の痛みを強く感じやすくなる傾向にあります。
奥歯が痛いときの対処法

奥歯が痛むときは、以下のような対処法を試してみましょう。
- 鎮痛薬の服用
- 痛む部分を適度に冷やす
- 口腔ケアで口内を清潔な状態にする
それぞれ解説します。
鎮痛薬の服用
奥歯の痛みの緩和には、鎮痛薬が有効です。用量・用法を守り、正しく服用しましょう。
なお、鎮痛薬はあくまで一時的な応急処置であり、原因の根本的な解決にはなりません。
痛みが治まった場合でも放置せず、早めに歯科医院を受診しましょう。
痛む部分を適度に冷やす
冷たいタオルや保冷剤をタオルで包み、頬の外側から短時間冷やすと、炎症を抑えるのに役立ちます。
ただし、冷やしすぎると逆効果になる可能性があるため、注意が必要です。
1回につき15〜20分ほどを限度にし、再度冷やす場合は時間を置いてからにしましょう。
口腔ケアで口内を清潔な状態にする
細菌によって痛みが引き起こされていることもあるため、歯磨きやうがいによって痛みを緩和できる可能性があります。
刺激を与えすぎないよう注意しながら、歯ブラシによるブラッシング、歯間ブラシやデンタルフロス、殺菌作用のあるうがい薬などを活用し、口腔内を清潔に保ちましょう。
歯科医院を受診し、セルフケアでは清掃が難しい部分まできれいにできる専門的なクリーニングを受けるのもおすすめです。
奥歯が痛いときに避けるべき行動

以下のような行動は奥歯の痛みを悪化させたり、長引かせたりする可能性があるため避けましょう。
- 血行を促す行動(入浴、サウナ、激しい運動、飲酒)
- 極端に熱い・冷たい食べ物、刺激物、甘いジュースなど
- 喫煙
- 刺激になる行動(痛む箇所を指や舌で触る、歯を強く噛み締める行動を繰り返す)
虫歯じゃないのに奥歯が痛むときは何科を受診すべき?

虫歯ではないと考えられる場合でも、奥歯が痛むときにはまず「歯科医院」を受診しましょう。
自分では「虫歯ではない」と思っていても、被せ物と歯の隙間から虫歯菌が入り込み、見えない虫歯になっている可能性も考えられます。
歯や歯茎に原因がないことを確認するためにも、自己判断せず早めに歯科医院を受診しましょう。
まとめ
奥歯が痛む原因は、必ずしも虫歯とは限りません。歯や歯茎に問題がある場合だけでなく、筋肉、神経、気圧などさまざまな原因が潜んでいます。
放置すれば悪化して痛みが強くなり、抜歯が必要になるケースもあります。自己判断せず、まずは一度歯科医院を受診することが大切です。
お花茶屋ハル歯科・矯正歯科では、口腔外科で習得した知識・技術を生かし、痛みに配慮した治療を心がけています。
徹底した衛生管理のもと、CTなどの先進検査機器による精密な診断を行っておりますので、虫歯ではないと思われる歯の痛みにお悩みの方はぜひ当院にご相談ください。
